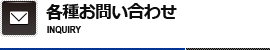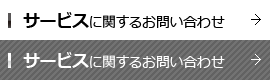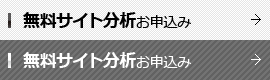読書の秋、デジタル社会の喧騒から離れて ~文化の日、岡本太郎・石津謙介・花森安治生誕百年に想う「挑戦」すること~
投稿者:小川 悟
2011/11/03 13:34
この記事は約13分で読むことができます。
「渋谷に西武が出てきた役割というのは、単一資本の街づくりが陥りがちなワンパターン化傾向に対して、他資本がアンチテーゼを出していく、絶えず刺激を与えていくということにより、街を活性化していく」
/『SEEDレボリューション 西武セゾングループのファッション潮流への挑戦と実験』(西武百貨店文化教育事業部編)
本日、11月3日は文化の日ですね。
私たちの仕事は、中小・ベンチャー企業向けWebコンサルティングということで、当然ながら日々の仕事にパソコンは付き物で、特に私のような内勤がメインの仕事となると帰宅後も含めて毎日10時間以上、パソコンの画面を見ていることもしばしばです。
やはり、こういう業界にいると、こんな日くらいはパソコンから離れて読書でも、と思いたくなります。森信三氏は読書を「心の食物」と表現(cf.『修身教授録』/森信三著)されましたが、日本国憲法に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という件もあります。
このような時期、待っていて必ずしも享受できるものとも限りませんので、自ら摂りにいくといった次第です(笑)。身体への気遣いは多くの人が自発的に実践されていると思いますが、心の方も同様にセルフケアを実践するといった意味で、私にとっては読書はその一つになるのかもしれません。
それから、極めて私事ではありますが、先般、事情により6年近く住んだ渋谷の地を離れることとなりました。今回のコラムでは、ビジネス的な話から少し離れ、当社本社のある渋谷へ対する個人的、感傷的な思いも織り交ぜつつ(笑)、文化の日ということでもあるので、表題にあります私が学生時代より興味を持ち続けている岡本太郎氏、石津謙介氏、花森安治氏という同じ1911年生まれの3人の文化人について書こうと思います(cf.『マーシャル・マクルーハン生誕百年、「メディアはメッセージである」 ~4月、当社第11期スタート、当社公式サイトスマートフォン対応化完了~』)。
まず、岡本太郎氏について。
忘れもしない2008年11月18日、当社本社のある渋谷に、氏の巨大作品「明日の神話」が誘致されました。JR改札から渋谷マークシティに抜けた吹き抜けの壁面を利用してぴったりフィットしています。この作品の招致合戦にはいろいろあったことと思いますが、渋谷在住の私にとっては目の当りにする機会が増えたので嬉しい限りでした。
氏を知らない人でも「芸術は爆発だ」という言葉はよく知られていると思います。普通は、何か荒々しいことを連想し、風変りな人だという印象を持ちそうです(風変りであったとは思いますが)。しかし、氏の養女として長年付き添った故岡本敏子氏によれば、この「爆発」は、自身の内から沸き起こるもっと静かな閃き――換言すればインスピレーションのようなものを言っているそうです(cf.『芸術は爆発だ!―岡本太郎痛快語録』/岡本敏子氏)。
岡本敏子氏がお亡くなりになられてすぐの2005年5月27日、『たけしの誰でもピカソ』というテレビ番組で『“せつなくも うれしく 恋しい人” 敏子が愛した岡本太郎』という特集が組まれたことがありました。この番組内で先の「明日の神話」のエピソードが登場するのですが、実はこの作品、諸事情により長らく行方不明になっていて、2003年にメキシコ国内で発見されるのですが、岡本敏子氏が30年来探し続けたと言われる稀少な作品であったのです。まるで、この作品を探し出すことが自身の使命と言わんばかりに、ようやく日本に持ち帰れるかどうかというときにお亡くなりになってしまいました。
東京・青山にある「岡本太郎記念館」は、岡本太郎氏が生前に自宅兼アトリエとして使用しており、没後に敏子氏が館長を務める記念館となりました。岡本太郎記念館は、表参道駅から根津美術館の方向に歩いていく道すがらの閑静な住宅街の中にあり、私もブルーノート東京のライブに行く前に、少し早めに出て岡本太郎記念館でコーヒーを飲んで逸る気持ちを落ち着けることが時々あったのですが(笑)、岡本敏子氏が生前の頃はよく顔を出されていて、満面の笑顔で訪れた人たちに気さくに声を掛けられる様子が印象的でした。
今年2011年は、岡本太郎生誕100年ということでドラマ化されたり、岡本太郎記念館をはじめ各地でイベントが行われていましたが、私も東京国立近代美術館や渋谷パルコで開催された展覧会を訪れたものでした。
さて、この岡本太郎氏、芸術家としての顔の他に、先の「芸術は爆発だ」にも見られるように、独特な考え方や言葉も有名で、後日語録なども多く刊行されました。その中に、『強く生きる言葉』や『壁を破る言葉』というものがあります。
挑戦した不成功者には再挑戦者としての新しい輝きが約束されるだろうが、挑戦を避けたままオリてしまったやつには新しい人生などはない。
/『強く生きる言葉』(岡本太郎,岡本敏子著)
現代のような、困難な時代に立ち向かう際に勇気を与えてくれるということで、昨今再評価を受けることがある氏だそうですが、この2冊を読んで片鱗に触れるだけでも元気になれることと思いますので、機会があれば是非手に取ってみて下さい。
続いて、石津謙介氏について。
「駅前には広場があって、その光景は地方都市のどこにでも見られるようなものと変わらない。そして岡山名物のふたつの立像が距離を隔てて建てられている。ひとつは岡山といえば桃太郎というくらい有名な、その桃太郎が犬と雉と猿を引き連れている立像、もうひとつはバンカラ・スタイルの弊衣破帽の学生像である。」
/『VANストーリーズ―石津謙介とアイビーの時代』
2007年に私用で直島を訪れたことがありましたが、後日上記の本を読んだ際、途中立ち寄った岡山駅舎前で「ここが石津謙介氏の生まれ故郷か」と感じたことを思い出していました。
氏は、「VAN」ブランドで知られる、株式会社ヴァンヂャケット(前身は「石津商店」)の創業者で、先の岡本敏子氏がお亡くなりになられた約1か月後の2005年5月24日にお亡くなりになられてしまいました。
「VAN」ブランドは割と好きな方で、ファッションに疎い私も、VANの赤いスウィングトップや、絶版本の『VANグラフィティ アイビーが青春だった』等の関連書籍などは所有しています。
ファッション界で「アイビー」と言えば、いわゆる「アイビーファッション」、「アイビールック」と呼ばれる、アメリカの「アイビー・リーグ」からとられて流行したスタイルの一つですが、50年代、60年代頃に日本で最初に紹介をしたのが氏です。
雑誌「平凡パンチ」が創刊された60年代、東京・銀座のみゆき通りに、当時にしては変わったファッション――、この「平凡パンチ」を片手に持って、女性はロングスカートに大きな紙袋、男性はコットンパンツかバミューダショーツといった格好をして集まる若者がいて俗に「みゆき族」と呼ばれていたそうですが、彼らの着ていたのがVANであり、持っていた紙袋こそがVANのロゴが入った紙袋でありました。
あまりに多くの若者が通りを占拠するため、現地警察が動き、石津謙介氏に何とかするように依頼したことがあるそうです。そのエピソードから誕生した氏の有名な言葉が、「僕は消えて行く流行ではなく、日本に定着する風俗を創ろうとしたのだ」というものです。
そんなVANブランドも、皮肉なことに時代の波か、賛否問われる経営手腕のためか、1978年4月6日、当時にして500億円の負債総額を抱えて倒産してしまいました。戦後、アパレル業界最大の大型倒産と、当時のファッション界で話題になったニュースだったようです。
cf.「墜ちた“中国ビジネスのカリスマ”女社長 その華麗な半生の虚実」(2011年11月3日,「MSN産経west」)
昨今もアパレル業界で大型倒産がありましたが、そういったものとは全く性質を違え、巨額の負債を抱えても復活を望む人々の声が消えず、多くのファンの期待に応えて見事再生を遂げたのが先の株式会社ヴァンヂャケットでした。
もちろん、75年生まれ世代の私にとってはタイムリーに知らない話ばかりですが、実は氏の遺したDNAは至るところで見つけることができます。
『MEN’S CLUB』(ハースト婦人画報社)というファッション誌があるかと思います。2004年に創刊50周年を迎えた老舗雑誌ですが、前身を『男の服飾』(『婦人画報』の男性版に当たる)と言いました。63年に『MEN’S CLUB』と誌名を変えた頃、本誌は「VAN」のPR誌と言われるほど特集を組むなどしていたようですが、そこに氏が動いていたと言われています。
私の世代以前の方には馴染みもあると思われる、雑誌『POPEYE』(マガジンハウス)や『Hot-Dog PRESS』(講談社)などの雑誌でも、かつて「アイビー」に関する特集が組まれていたことがあるようです。『Hot-Dog PRESS』で「アイビー」の特集が組まれた頃の話については、『アイビーは、永遠に眠らない 石津謙介の知られざる功績』に詳しいです。著者は、『Hot-Dog PRESS』の創刊プロデューサーで、79年の創刊から88年までの間、同誌のエディトリアル・ディレクター、ファッション・ディレクターを務めた花房孝典氏です。
他にも男性ビジネスマンなら少なくとも1着は持っていると思われる「ボタンダウンシャツ」、これをトラッド/カジュアルシーンに登場させたのはブルックス・ブラザーズが発祥と言われていますが、そのBDシャツを日本で定着させたのが氏と言われています。
また、今でもJR渋谷駅から渋谷マークシティに入り、道玄坂に抜ける手前にある「メーカーズシャツ鎌倉」、鎌倉本店をはじめ全国各地に店舗があります。「上質のシャツを、4900円で販売する」というコンセプトで、利用されるビジネスマンの方も多いのではないかと思いますが、ここでシャツなどを買うと「石津謙介」という手書きの文字が入ったカードが一緒に入ってきます。
そこには、「私の門下生、貞末君夫妻がシャツショップを始めるという――」で始まる文章が書かれていますが、ここで「貞末君」と書かれているのが「メーカーズシャツ鎌倉」の創業者であり、一般社団法人日本メンズファッション協会(MFU)理事の貞末良雄氏です。貞末氏は、元ヴァンヂャケットの社員だったのです。
以上、こんなところにまでという印象もあると思いますが、そのようにして「VAN」のDNAは現代にも受け継がれているのだと思います。
大阪のアメリカ村は「VAN」発祥の地ですが、現在、株式会社ヴァンヂャケット本社が置かれるのは東京・青山です。そこから歩いてすぐ近くにある表参道交差点にある山陽堂書店では、今月7日まで氏に関する簡単な展示をおこなっており私も訪れました。
まだ数日ありますので、今も昔も一部男性諸氏を虜にしたファッション界のカリスマ、石津謙介氏にご興味があれば是非訪れてみて下さい。
最後に、花森安治氏について。
氏は、1948年9月、東京・銀座にて、生活誌『暮しの手帖』を、現暮しの手帖社社主の大橋鎮子氏とともに創刊した編集長です。先述のヴァンヂャケット社が倒産する少し前の、1978年1月にお亡くなりになられています。
2008年2月、主婦の友社刊の婦人誌・生活誌の『主婦の友』が休刊し、91年の歴史に幕を閉じたニュースは、出版不況の代名詞のように伝わったものでしたが、そうした中で私は、根強く特定の読者層を抱えるこの雑誌に興味を持っていたことがありました。
一番興味を持ったのは、この雑誌の最大の特徴でもある、「創刊以来、一切広告を載せていない雑誌」であるという点でした。学生時代の私が考える雑誌というのは、雑誌の販売売上もありますが、多くは広告収入で成り立っているビジネスモデルだという認識があったので、「なぜ広告を載せない雑誌が、こんなに長い間、発行され続けているのだろう」という単純ですが、強い疑問があり、それが興味の対象になっていったのを記憶しています。
広告を掲載しない理由は、氏が広告嫌いだったのではなく、自社広告は載せています。自身でミリ単位まで気を使ってレイアウトした誌面に他社の純広告が割って入るのを嫌っただけで、新聞広告は自身で作り、誌名のロゴも毎号新しく書かれていたそうですが、氏の手書き文字によるコピーやデザインにはユニークなものが多いです。
この「広告がない」ということにも関連するのですが、もう一点有名な特徴として挙げられるのが本誌の一コーナー「商品テスト」です。
これは、生活者視点に立ち、当時市場に出ていた家電製品や石油ストーブ、靴下から鉛筆に至るまで、本当に安全で良い製品なのかどうかを編集部でテストして、誌面上で公開するというコンテンツでした。
売手市場であった高度成長期、有名メーカーの製品にケチでも付けようものなら、広告出稿が止まってしまうことなど簡単に起こった筈ですが、本誌は創刊以来というもの広告は一切掲載しない方針であるため、そういった商業的なリスクヘッジは不要ということで、徹底的に商品をテストします。
氏の考え方としては「商品テストは消費者のためではない。メーカーのためだ」(cf.『花森安治の編集室』/唐澤平吉著)というものでした。
<商品テスト>は、消費者のためにあるのではない――このことを、はじめに、はっきりとさせておかねばならない。
(中略)メーカーに主義主張はない。売れるものを作るだけである。よい商品を作れば売れる、となれば、一生けんめいよい商品を作る。
/『暮しの手帖 保存版III 花森安治』(暮しの手帖社発行)
結果論としてかもしれませんが、広告主に媚びるのではなく逆に徹底的に生活者(消費者)に寄る、こうしたユニークな方針が本誌の強みとなって、今日に見られるような特定の名声を稼いだのでしょう。一万部から始まり、一時は九十万部まで発行部数を伸ばした雑誌のようです。
この「商品テスト」がどれだけメーカーに響いたかは分かりませんが、その後、日本のものづくり界は品質を高めていき、世界トップクラスの品質基準で検品作業をおこなう国にまでなりました。
cf.煙を嗅ぎながら延焼を体感「死に様試験」/日立アプライアンス(2011年10月24日,「日経情報ストラテジー」)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20111017/370918/
昨今、日本のものづくりが振るわないという暗いニュースも多いですが、品質が良いという部分では世界でも秀でていると感じます。「良いモノを作る」という気持ちは、引き続き作り手として強く持ち続けていたいと改めて感じました。
以上、今年もまもなく終わりに近づいていますが、今年生誕百年になる3人の文化人について挙げてみました。
いずれの方も辿られた人生を今振り返ってみて、困難や壁に当たらず楽に生きてきた方はいなそうです。つまり、今現在が最も困難な時代であるかのように感じてしまうこともあるのかもしれませんが、もしかすると、困難の絶対性で言えば今も昔も変わらず、今を生きる当事者が皆、常々感じる共通感覚なだけなのかもしれない、とふと思いました。
また、常に挑戦できる目標や競争相手があるからこそ「挑戦」できるし、その過程を経て自身や自社が成長するのであって、逆に見ればしっかりと目標に向かって突き進む以上は、そうした目標や相手に引っ張り上げてもらえているということになるのかもしれませんね。
要は心の持ち様だということで、文化の日、2011年秋の収穫として得たものを書くことで、本コラムを締めさせて頂きます。